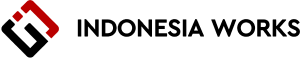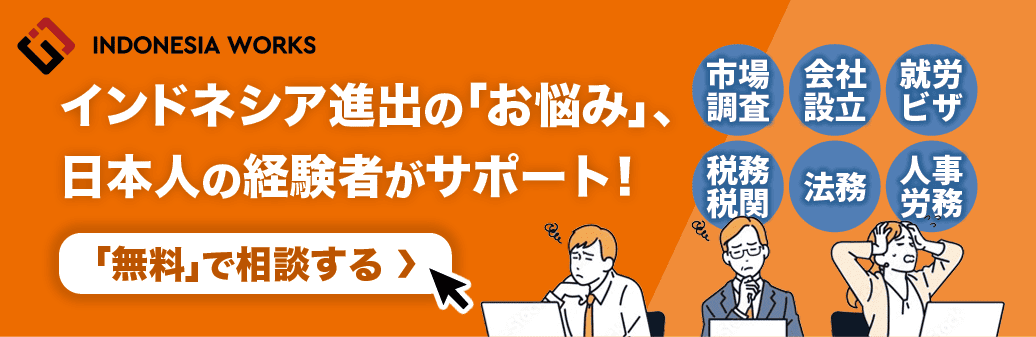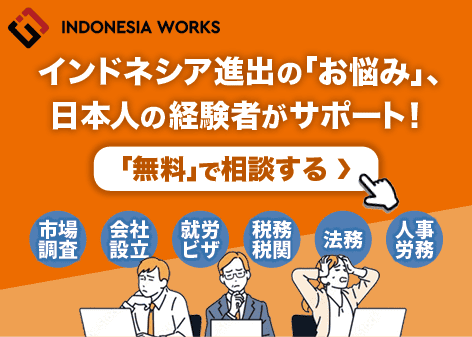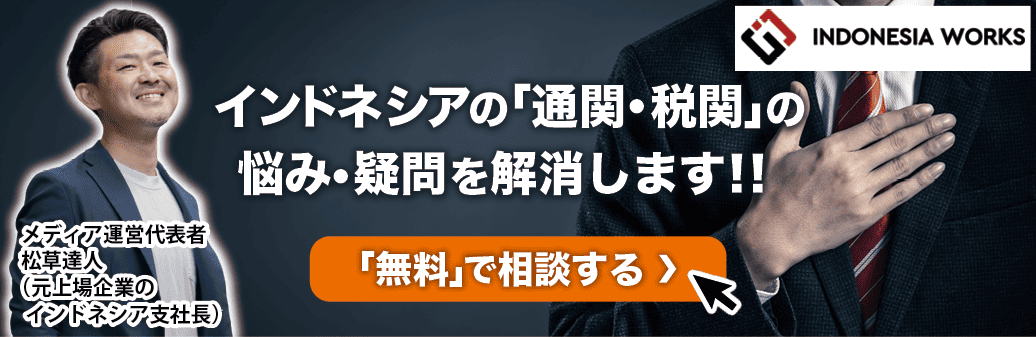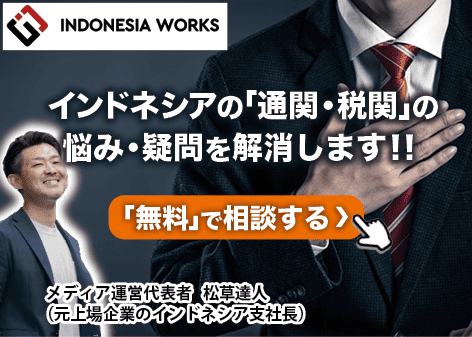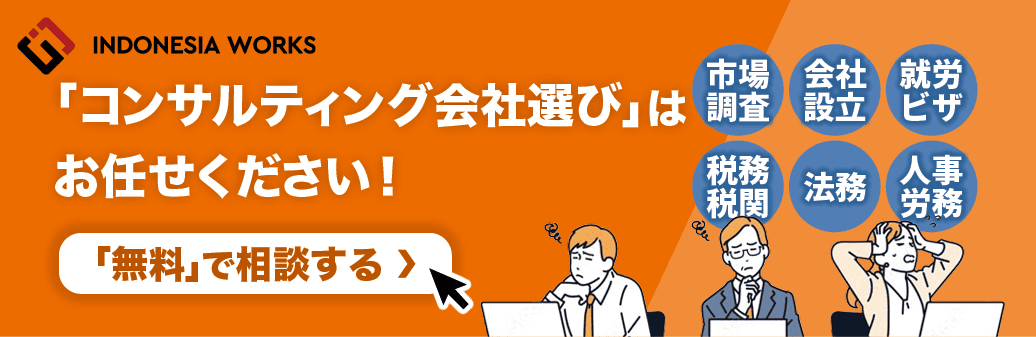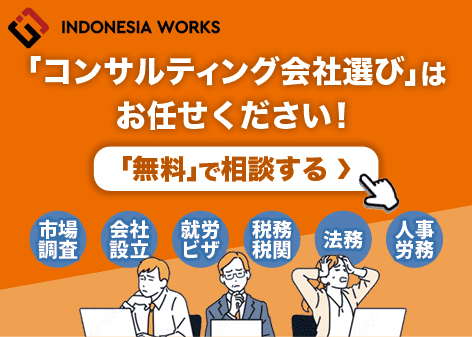本記事ではインドネシアの通関に関する「よくあるトラブル事例」を、大きく3つのケースに分けて紹介します。
<インドネシアでよくある通関トラブル>
- 「追徴課税が課せられてしまった」トラブル事例
- 「輸入品が通関で止まってしまった」トラブル事例
- 「日本・インドネシア経済連携協定」に関するトラブル事例
また、下記記事では「通関・税関手続きのやり方」や「手続きを依頼できるコンサルティング会社」について解説しています。あわせてご確認ください。
1.「追徴課税が課せられてしまった」トラブル事例

まずは「追徴課税」が課せられてしまったトラブルの事例を紹介します。
<追徴課税が課せられてしまったトラブルの事例 一覧>
| トラブル事例 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 日本のHSコードを利用したら、インドネシアと解釈が異なり、追徴課税が発生した | 同じ品物でも、日本のHSコードとインドネシアでのHSコードが違い、通関で認められず、追徴課税を課せられることがあります。 |
| 2 | 利用できていたHSコードが事後調査で指摘を受け、高額の追徴課税が生じた | 定期的にインドネシアに商品を輸入していた際に問題なく利用できていたHS コードが、突然「不可」になるようなケースがあります。 |
| 3 | ライセンス回避のため実態と異なるHSコードを使用していたが、違いを指摘されて過去数年分の追徴金を支払った | ライセンス(輸入許可)が必要な品目に、回避の為異なるHSコードを使用するような不正を行うと、発覚時には過去数年分の追徴金を支払うこととなります。 |
| 4 | 関税の還付手続きを行ったら、別件で罰金を課せられた | インドネシアでは、払いすぎた関税の還付がほとんど成功しません。 むしろ、還付金申請を行うと税務監査が入って会社を徹底的に調査されることが多く、関税とは関係のない税法違反で追徴金を徴収される例もあります。 |
それぞれについて解説します。
1-1. 「日本のHSコードを利用したら、不適切」と指摘された事例
トラブル内容
日本での輸出申告に使用したHSコードでも、インドネシア通関では認められない場合があります。
対応策
HSコードの決定権は「輸出側は輸出国の通関、輸入側は輸入国の通関」にあります。
そのため、輸出事業者が通知してきたHSコードをそのまま使用して輸入手続きを進めると、インドネシア通関で指摘を受けたり、関税の追徴課税が発生したりするケースが多いです。
基本的に6桁のHSコードは、HS加盟国や使用国で共通のルールに基づいて分類されます。
しかし、同じ商品でも輸入国によって異なるHSコードに分類されることがあるので注意が必要です。
HSコードの分類には専門的な知識が求められるため、輸入トラブルが発生した後はもちろん、輸入を実施する前の段階でも、通関コンサルティング会社等を利用した方がよいでしょう。
参考:JETRO|HSコード
1-2.「利用できていたHSコードが事後に不適切とされた」事例
トラブル内容
日本からインドネシアへ商品を定期的に輸入する中で「問題のなかったHSコード」でも、インドネシア税関の事後調査で「輸入品とHSコードが異なる」と指摘されるケースがあります。
その場合、過去に遡っての追徴課税が課せられる可能性が高いです。
対応策
〈事後対応〉
最初にすべきことは、商品の詳細な資料を用意して通関に説明して理解を求めることです。
インドネシア通関が納得せずに追徴課税の納付を求められた場合は、一度追徴分を納付した後に異議申立てを行う方法があります。
仮に異議申立てが却下された場合、費用や労力がかかりますが税務裁判を起こすことも選択肢の一つです。
〈事前対策〉
インドネシア税関に事前教示の申請を行い、輸入品のHSコードと関税率を確認することができます。
事前教示決定書が発行されると3年間有効となるため、定期的に同じ商品を輸入している場合には事前教示制度を活用することが効果的でしょう。
1-3. 「ライセンス回避のため実態と異なるHSコードを使用したことが発覚」した事例
トラブル内容
ライセンス取得を避けるために実態と異なるHSコードを使用していても、いずれ発覚する可能性が高いです。
不正には厳しい罰則が適用されるため、非常にリスクの高い行為といえるでしょう。
対応策
ライセンス(輸入許可)が必要な特定の品目を輸入する際、特にインドネシアにおいては許可の取得に時間がかかり、手続きも非常に煩雑だったりするため、企業の輸入担当者がライセンス不要なHSコードを使って輸入申告を行い、許可の回避を試みてしまうことがあります。
実態と大きく異なるHSコードを使用して申告すると不正と見なされ、多額の追徴課税が課せられるなど厳しい罰則が適用されます。
正しいHSコードで輸入申告することはもちろん、インドネシアの複雑な輸入手続きを円滑に進めるためには、経験豊富で信頼できる輸入担当者を採用することも検討しましょう。
1-4.「関税の還付手続きを行ったら、別件で税法違反に問われた」事例
トラブル内容
インドネシアで払いすぎた関税を還付してもらったといった事例は、とても少ないです。
しかも、関税の還付金申請を行うと必ず税務監査に入られてしまうため、還付金申請が引き金となり会社を徹底的に調べられ、関税とは無関係な追徴課税を請求される可能性もあります。
対応策
通関を通す前に適切な手続きを行っておくことが重要です。
一度通関を通過した後は、どんな訂正でも何らかのペナルティが課される可能性が高いと考えておいた方がよいでしょう。
また、還付金申請での監査では「輸出入のVATに関する監査」だけではなく、「法人税を含む全体的な税務監査」へと発展するケースが多いです。
全体的な税務監査に発展してしまうと、対応する労力や諸費用がかかってしまうため、還付金額が少額であれば戦略的に還付金申請を実施しない等、戦略的な判断をした方がよい場合もあります。
2.「輸入品が通関で止まってしまった」トラブル事例

「輸入品が通関で止まってしまった」トラブルの事例を紹介します。
<「輸入品が通関で止まってしまった」トラブルの事例 一覧>
| トラブル事例 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 必要なライセンスを取得しておらず、通関が通らなかった | 通常必要なライセンス(API-P 等)だけでは通関しない輸入品目である事に気づかず、別途必要なライセンスを取得しておらず、通関が通らなかった。 |
| 2 | 新品を中古品として判断され、通関で止まった | インドネシアでは中古品の輸入は原則禁止されており、新品でも中古品と誤認されてしまうと輸入が認められません。 |
それぞれについて解説します。
2-1. 「必要なライセンスを取得しておらず、通関が通らなかった」事例
トラブル内容
輸入品目にはHSコードごとに規制や制限されているものがあり、品目によっては、輸入前に通常のライセンスとは別のライセンスを取得しておかないと、通関で止められ輸入できないケースがあります。
対応策
インドネシア国内に輸入する際、「API-P(製造業者向け)」や「API-U(非製造業者向け)」といった輸入事業者が保持すべきライセンスが必要です。
ただし、輸入品目ごとに「必要なライセンス」が細かく定められており、一般的な「API-P」や「API-U」以外にもライセンスが求められる輸入品目があります。
また、多くの輸送業者はライセンスの有無が不明な場合、そもそも輸送業務を引き受けません。インドネシアに輸入する前に「必要なライセンス」を、コンサルタント等に事前確認しておくことは必須です。
2-2. 「新品を中古品として判断され通関で止まった」事例
トラブル内容
インドネシアでは中古品に関する規制が厳しく、中古品と誤認されることを避けるため、多くの企業が輸出前に製品を加工・磨き直す「化粧直し」を行っています。
しかし、長時間にわたって高温多湿の環境下で輸送・保管されると製品に錆が生じて中古品と間違えられ、新品と認めてもらえなかったといったケースもあります。
対応策
中古品の輸入が禁止されているインドネシアでは、「錆」に対する注意が必要です。
高温多湿の熱帯気候の影響で、輸送途中や通関待ちの時間などで製品が錆びてしまうことがあります。
熱帯地域での錆防止には、乾燥剤だけでなく防錆紙を使ったラッピングが一般的です。
また、防錆油を塗布するなど防錆対策を施しても、熱帯地域では十分な効果が得られない場合があることに留意しておきましょう。
3.「日本・インドネシア経済連携協定」に関するトラブル事例

「日本・インドネシア経済連携協定」に関するトラブルの事例を紹介します。
<日本・インドネシア経済連携協定に関するトラブル事例 一覧>
| トラブル事例 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 「電子原産地証明書(e-CO)」がインドネシア税関に届かなかった | システムの不具合等により、日本から送信された「電子原産地証明書(e-CO)」がインドネシア通関で受信されない場合があります。 |
| 2 | 関税の特恵待遇が認められなかった | 日本とインドネシアの経済協定があるにもかかわらず、日本から第三国を経由してインドネシアに輸入すると、関税上の特恵待遇を受けられないケースがあります。 |
それぞれについて解説します。
3-1. 「届いてるはずの原産地証明書(e-CO)が、インドネシア通関に届いてない」事例
トラブル内容
日本・インドネシア経済連携協定(JIEPA)に基づく原産地証明書の運用方法が、2023年に紙から電子データに変更されました。
これにより「電子原産地証明書(e-CO)」は、輸入者が直接インドネシア通関に提出するのではなく、日本側の発給機関である日本商工会議所がインドネシア通関に電子データを送付する形になっています。
対応策
システムの不具合により日本側から送信された「電子原産地証明書(e-CO)」がインドネシア通関で受信されないケースがあります。
上記のような予期せぬ事態に備え、発給システム上にある原産地証明書のPDFファイルを印刷しておくことをおすすめします。
また、輸入事業者はインドネシアの公的サイト「INSW(INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW)」から、「電子原産地証明書(e-CO)」の受信状況を確認できます。
INSW上で受信が確認できれば、インドネシア通関に印刷した受信画面を提示することで、輸入通関を行うことも可能です。
<INSWのサイト>

参考: 日本商工会議所|日インドネシア協定における原産地証明書のデータ交換 (特定原産地証明書の電子化)に関する詳細のご連絡(vol.4)
参考:日本商工会議所|第一種特定原産地証明書発給申請マニュアル
3-2.「関税の特恵待遇が認められなかった」事例
トラブル内容
原産品を日本からインドネシアに第三国を経由して輸入した際、日本・インドネシア経済連携協定(JIEPA)に基づいた関税の特恵待遇がインドネシア通関で認められない場合があります。
対応策
一つまたは複数の第三国を経由して輸入する場合、「通し船荷証券」や「特定原産地証明書」に経由地や積替え後の船名が記載されていないと、特恵待遇が認められないケースがあります。
対策としては、
- 「通し船荷証券」「特定原産地証明書」に経由地等を記載する
- 「通し船荷証券」に「Through Bill of Lading」と記載する
ことをおすすめします。
上記の対策を講じても、インドネシア税関から何らかの指摘を受ける可能性はありますが、記載していない場合よりは特恵待遇が認められる可能性が高まります。
「インドネシアでのビジネスの始め方」関連記事
- インドネシア進出の流れ・手順とやるべき事を段階別に解説
- 【インドネシア進出を検討する企業向け】市場調査と実行可能性調査(F/S)の方法・費用相場をまとめて解説
- インドネシアでの会社設立「どれを選べばいいのか」がわかる|設立・進出形態の比較一覧
- 【基礎から解説】インドネシアで日系企業が会社設立する手順・費用&必要書類
- 【簡単解説】インドネシアで内資法人(PMDN)を設立する手続き・手順&費用
- インドネシアで「ノミニー利用」をするべきかどうかを徹底考察
- 【簡単解説】インドネシアで駐在員事務所を開設する手順・費用&必要書類
- 【簡単解説】インドネシアでの雇用代行(EOR)サービスについて
- 【簡単解説】インドネシアの法律・法的規制 一覧
- 日本とインドネシアの「労務関連法規の違い」 比較一覧
- 【雇用・給与編】インドネシアの人事・労務に関するトラブル事例集
- 【労働組合編】インドネシアの人事・労務に関するトラブル事例集 その2
- 【初心者向け】インドネシアの税務・税制について
- インドネシアでの税理士・会計事務所の選び方
- インドネシアでの通関・税関(輸出入)手続きのやり方について
- インドネシアの通関・税関トラブル事例集
インドネシアビジネス 必読記事