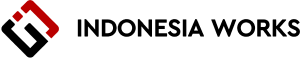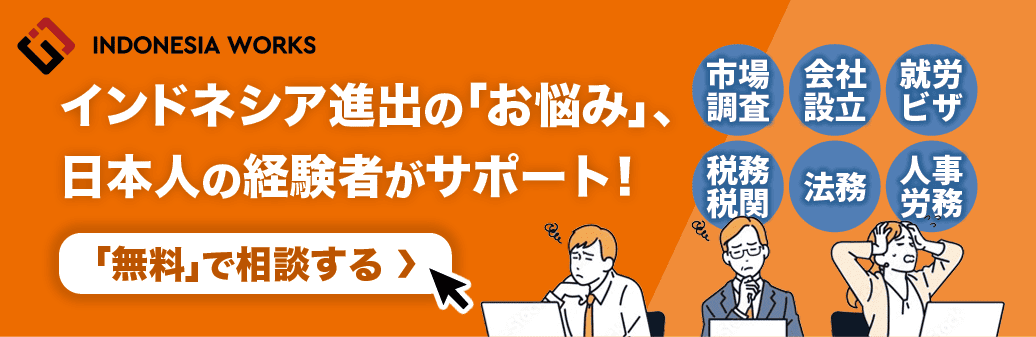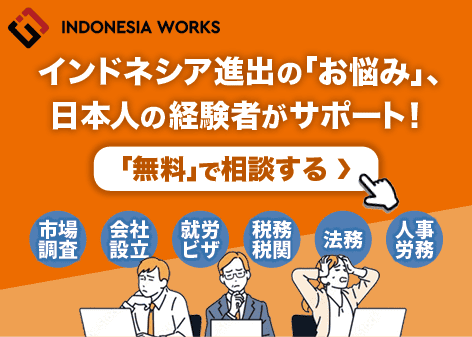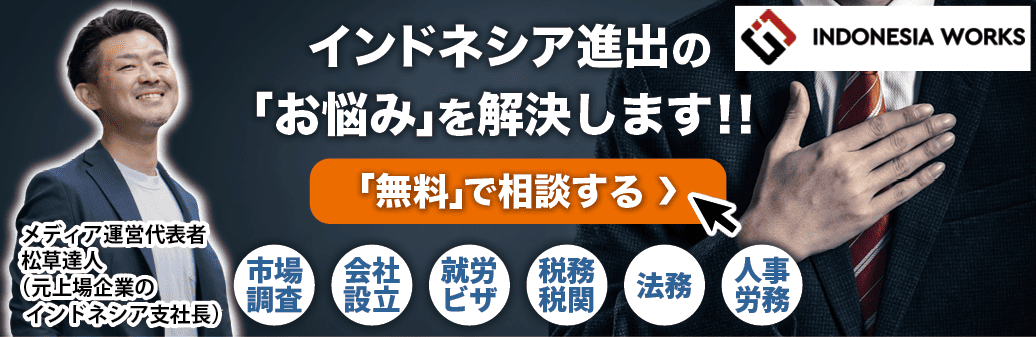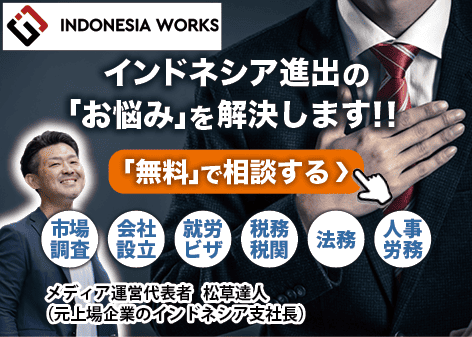本記事では、インドネシアに進出する際に必要な基礎知識をまとめて解説します。
また、インドネシアでのビジネスの具体的な始め方や、重要なマクロデータについては、下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
1.【最新】インドネシアの基礎知識
インドネシアの基礎知識を「基礎情報」と「マクロ経済情報」に分けて、紹介します。
1-1.インドネシアの基礎情報
インドネシアは「人口が日本の2倍以上」「面積が日本の約5倍」の規模を誇ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約2億7,000万人(2020年:世界4位) |
| 面積 | 約192万平方キロメートル |
| 首都 | ジャカルタ |
| 通貨 | インドネシア・ルピア(Rupiah) 1ルピア=0.0095円(2024年3月) |
| 民族 | 約300(ジャワ人、スンダ人、マドゥーラ人等マレー系、パプア人等メラネシア系、中華系、アラブ系、インド系等) |
| 主な言語 | インドネシア語 |
| 宗教 | イスラム教 86.69%、キリスト教 10.72%(プロテスタント 7.60%、カトリック 3.12%)、ヒンズー教 1.74%、仏教 0.77%、儒教 0.03%、その他 0.04%(2019年、宗教省統計) |
引用:外務省|インドネシア共和国(Republic of Indonesia)基礎データ
インドネシアでは首都ジャカルタがあるジャワ島に、人口の約7割が居住しています。
ジャワ島とジャワ島以外での経済格差や首都ジャカルタへの一極集中が長年の課題とされており、カリマンタン島の「ヌサンタラ」への首都移転計画が進行中です。
〈図 ジャカルタとヌサンタラ〉

1-2.インドネシアのマクロ経済情報
インドネシアの最新のマクロ経済情報を紹介します。
インドネシアはタイやベトナムなどASEAN諸国の中で突出した経済規模を誇ります。
貿易額は低く、世界4位の人口を基盤とした内需大国です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| GDP(名目) | 約1兆4,200億ドル(2023年:世界16位) |
| 一人あたりGNI(名目) | 4,656ドル(2022年) |
| 実質GDP成長率 | 5.0%(2023年) |
| 消費者物価指数 | 2.6%(2023年) |
| 平均賃金 | 377ドル (日系企業で働く製造業〈作業員〉の場合) |
| 賃金上昇率 | 5.5% |
| 失業率 | 5.32%(2023年8月) |
| 貿易額 | 輸出:約2,588億ドル(2023年) 輸入:約2,218億ドル(2023年) |
| 主な輸出品目 | 鉱物性燃料(435.72億ドル)、動物・植物性油脂等(284.54億ドル)、石油・ガス(159.22億ドル) |
| 主な輸入品目 | 石油・ガス(358.3億ドル)、機械・機械設備(321.55億ドル)、電気機器(約257.82億ドル) |
| 主な輸出先 | 中国、アメリカ、日本、ASEAN諸国 |
| 主な輸入元 | 中国、日本、アメリカ、ASEAN諸国 |
| 主要産業 | 製造業(19.2%) 卸売・小売(13.4%) 農林水産業(13.0%) 鉱業(12.8%) 建設業(10.2%) 運輸・倉庫(5.3%) 金融・保険(4.3%) 情報通信(4.3%) 行政・公共・防衛(3.2%) 教育(3.0%) 不動産(2.6%) 宿泊・飲食(2.5%) 事業サービス(1.8%) 電力・ガス・水道(1.2%) その他サービス(3.2%) |
引用:外務省|インドネシア共和国(Republic of Indonesia)基礎データ
引用:インドネシア中央統計庁
引用:IMF|Real GDP growth
引用:JETRO|2023年度海外進出日系企業実態調査 アジア・オセアニア編
インドネシアはASEAN諸国の中でも一人あたりGNIは低いですが、実質GDP成長率は堅調に推移しています。
さらに世界で4番目に大きな人口を有する内需大国なため、今後大きく成長する可能性が高い市場として魅力的です。
これらマクロ環境情報について、下記でより詳しく解説しています。
1-3.インドネシアのビザ情報
日本国籍の方がインドネシアに入国する際、
滞在日数や入国目的を問わず、必ずビザ(査証)が必要です(2025年3月現在)
なかでも、日本国籍の方が最も取得しやすく、利用頻度が高いのは「インデックスB・到着ビザ」で、30日以内の旅行や商用目的で多く利用されています。
インドネシアのビザ事情について、下記記事で詳しく解説しています。
2.インドネシアに進出するメリット
日本貿易振興機構(ジェトロ)の調査(2022年)よると、現地でビジネスを展開している日本企業の多くが、インドネシア市場の「成長性」と「市場規模の大きさ」に魅力を感じています。
<インドネシアでビジネスする魅力>
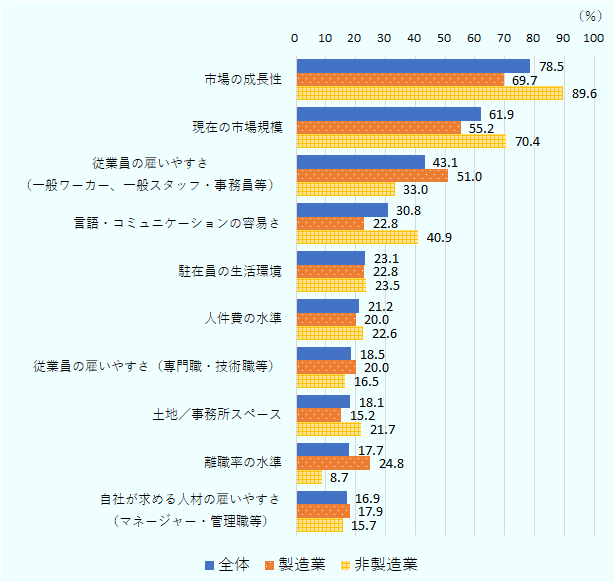
引用:JETRO|拡大する市場は魅力も、国産化優先政策が投資環境上のリスクに(インドネシア)
これらの「魅力」を読み解くと、インドネシアに進出する日本企業は主に、
- 今後、一層の経済成長が期待される、巨大市場を事業成長に取り込める
- 膨大な若年人口、急ピッチで進む資源開発、地理的な好条件等、潜在的にビジネスチャンスが数多くある
- 安価な労働力、親日国である、投資受入れ環境の整備を進めている等、日本企業の進出に向いた条件がある
事をメリットとして捉えていると言えます。
その内容は、以下のとおりです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 今後の経済成長を事業成長に取り込める |
|
| 多くの人口を持つ巨大市場を事業成長に取り込める |
|
| 「膨大な若年人口」というビジネスチャンスがある |
|
| 急ピッチで進む資源開発等のビジネスチャンスがある |
|
| 地理的な好条件 |
|
| 安価な労働力がある |
|
| 親日国であり、強い経済関係がある |
|
| 政府が、外国からの投資受入れを促進している |
|
上記のようなメリットを背景に、日本貿易振興機構(ジェトロ)の調査(2022年)によると、インドネシア進出している7割以上の日本企業は、営業利益が黒字の見込みです。
さらに、今後1〜2年のうちに、事業拡大する予定のある企業は約48%にのぼります。
3.インドネシアに進出するデメリット・リスク
日本貿易振興機構(ジェトロ)の調査(2022年)よると、インドネシアの日本企業は「税務手続き」や「法制度」、「行政手続き」などインドネシア特有の問題にビジネス的なデメリット・リスクを感じています。
<インドネシアでビジネスするデメリット・リスク>
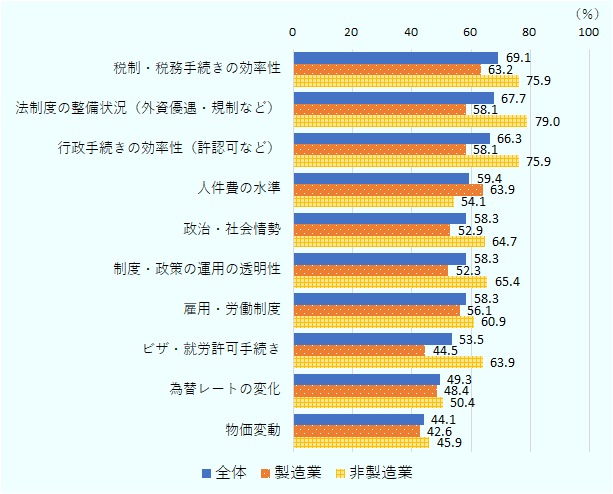
引用:JETRO|拡大する市場は魅力も、国産化優先政策が投資環境上のリスクに(インドネシア)
また、変化が激しいマクロ環境やインフラ整備の遅れも、進出時のデメリットとして考えられます。
具体的な内容は、以下のとおりです。
| デメリット・リスク | 内容 |
|---|---|
| 法規制の内容や執行基準が曖昧で、事業がリスクにさらされやすい |
|
| 日本ではなじみのない労働規制が様々あり対応に労力がかかる |
|
| コンプライアンス上の問題が発生しやすい |
|
| マクロ環境の変化が激しく対応が難しい |
|
| 文化的な違いに対応する為の労力やコストがかかる |
|
| 脆弱なインフラで「時間的なロス」の発生が多い |
|
デメリット・リスクの詳しい内容は下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
4.日本企業のインドネシア進出状況
外務省の調査によると、2022年10月時点でインドネシアに進出している日本企業は合計で2,103社にのぼります。
進出企業の中で全体の約50%が製造業となり、次いで「卸売業、小売業」、「サービス業」が続きます。
詳しい業種や進出場所はこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
4-1.成功する企業の特徴
インドネシアビジネスで成功する企業には、以下のような特徴があります。
- どの国の競合より、いち早く進出する
- 現地の文化や消費者ニーズを理解するための徹底的なマーケティングを行う
- 地域ごとの需要に合わせた商品の提供をする
- 健全な経営基盤を持つ現地パートナーと協力体制を作る
成功する企業の多くは、インドネシアで未開発の市場を見つけ出し、どこよりも早く進出しています。
また、現地パートナーとの協力体制を築き、消費者ニーズを的確に捉えている点も共通点です。
4-1-1.インドネシア進出で成功している企業の事例
ここでは、インドネシア進出で成功している企業の事例を2つ紹介します。
成功事例①:ヤクルト|1日の販売本数は約700万本

引用:PT.Yakult Indonesia Persada
乳酸菌飲料メーカーとして国内最大手のヤクルトは、インドネシア進出で成功した企業の一つです。
ヤクルトは1991年からインドネシア市場に参入しました。
西ジャワ州と東ジャワ州にはそれぞれ工場を構え、1日あたりの販売数は700万本を超えています。
日本では複数の商品を展開しているヤクルトですが、インドネシアでは商品数を絞り、「商品の価値」を地道に普及し続けた成果といえます。
また、インドネシア全国に1万人を超えるヤクルトレディによる営業活動も大きな特徴です。
結果、ヤクルトにとってインドネシア市場は日本に次いで大きなマーケットとなっています。
成功事例②:ピジョン|インドネシアでの哺乳瓶のシェアは60%以上
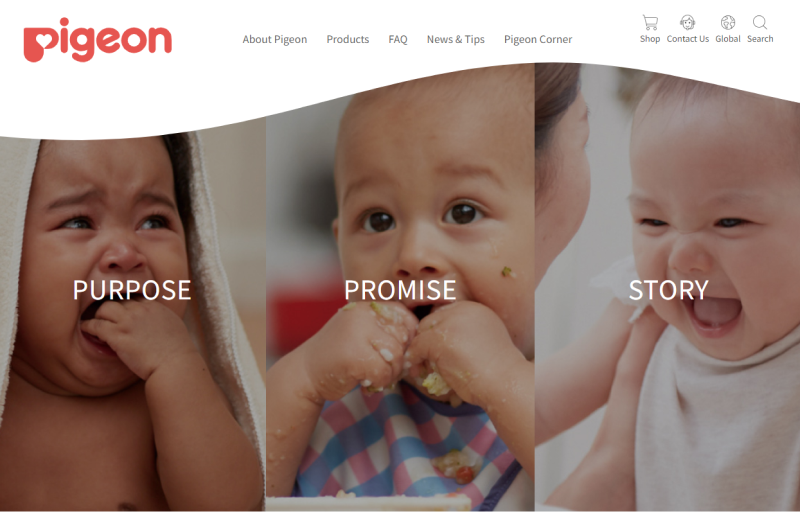
引用:PT PIGEON INDONESIA
ベビー用品を幅広く扱うピジョンもインドネシアに進出し、成功を収めた企業の一つです。
ピジョンは、インドネシアの販売代理店への日本製哺乳瓶の輸出から事業をスタートしました。
1995年には現地の企業と合弁で、プラスチックとシリコンの成形工場を設立し、哺乳瓶の製造を開始しました。
品質と安全性に重点を置いた製品開発と、現地生産によるコスト競争力を活かし、高い市場シェアを確保しています。
現在では現地で製造された製品のうち、60%がインドネシア国内用に、残りの40%が海外に輸出されています。
他のインドネシア進出の成功事例は下記記事で紹介しています。あわせてご確認ください。
4-2.失敗する企業の特徴
インドネシアビジネスで失敗している企業には、以下のような特徴があります。
- 競合の進出に焦りを感じ、突発的に参入を決める
- 適切な情報収集をすることなく、進出する
- 現地の文化等を考慮せず、日本で売れているものを販売する
- 本社の意向を過度に聞きすぎる
- 日本と異なる商習慣やスタッフとのコミュニケーションに対応できない
特に突発的な進出や不十分な情報収集のまま進出を決めると失敗することが多々あります。
インドネシア進出の際は、現地の市場動向や文化、価値観など多角的な視点から情報を集め、計画的に行動することが必要です。
また、経営の最終決定権が本社にある場合は、現地での迅速な判断が困難になり、ビジネスチャンスを逃すケースも少なくありません。
4-2-1.インドネシア進出で失敗した事例
インドネシア進出で失敗した事例を2つ紹介します。
失敗事例①:飲食店|日本での成功モデルが通用しなかった事例
現地スタッフの働き方や料理のマニュアル運用が日本と異なることを理由に、一貫した品質を保つことが難しく失敗するケースが多いです。
特に、食べ物を提供する飲食店では、インドネシアの暑い気候の中において食中毒などのリスク管理が日本以上に重要となります。
人材管理や品質管理、リスク管理の面で日本での成功モデルが通用せず、やむを得ず撤退するケースがあります。
失敗事例②:農業|現地スタッフのマネジメントがうまく行かず失敗した事例
インドネシアの広大な土地や豊富な水資源を活用し農業を始めようとするも、現地スタッフとのコミュニケーションの問題で失敗するケースもあります。
具体的には、日本で流行りの農産物をインドネシアで生産、品種改良しても現地スタッフとのコミュニケーション不足により収穫物が行方不明になったり、食べられてしまったりすることも少なくありません。
農業に限らず、インドネシアでのビジネス成功には、現地スタッフとの良好なコミュニケーションが必要不可欠です。
他のインドネシア進出の失敗事例は下記記事で紹介しています。あわせてご確認ください。
5.インドネシアの宗教や商習慣・ビジネスルール一覧
インドネシアの宗教や商習慣、ビジネスルールについて解説します。
5-1.インドネシアの宗教と慣習
インドネシアでは、公的に認められた以下6つの宗教いずれかを信仰しなければなりません。
<公的に認められた6つの宗教>
- イスラム教
- キリスト教(カトリック)
- キリスト教(プロテスタント)
- ヒンズー教
- 仏教
- 儒教
なかでもイスラム教の信者は国内で80%を超えており、インドネシアは世界最大のイスラム人口を有しています。
5-1-1.食事や接待のマナー
インドネシアでは宗教が日常生活の基盤となっています。
例えばイスラム教徒やヒンズー教徒にとっては、食事に関する規定が厳格に定められており、口に入れる食材に対して非常に気を使います。
イスラム教では、豚肉や宗教上の適切に処理されていない肉、およびアルコールの摂取などが禁じられています。
ラードやゼラチン、豚が使われた調味料など豚由来の食べ物を口にすることもできません。
またヒンズー教では肉類(特に牛肉と豚肉)、魚介類、卵、および五葷(ニンニク、ニラ、ラッキョウ、タマネギ、アサツキ)が禁忌されています。
したがってビジネスシーンでよくあるランチやディナー、接待の際には、相手の宗教的な制約を適切に理解し、尊重することが重要です。
参考:国土交通省 観光庁|多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル
5-1-2.仕事中でも行う礼拝の習慣
イスラム教では日の出前と昼、午後、日没時、夜と1日に5回、メッカの方角を向いて礼拝を行う習慣があります。
礼拝は仕事中でも必ず行われており、職場には礼拝のための場所を設け、提供する必要があります。
また、毎日の礼拝の中でも、金曜日の礼拝は特別なものとされています。
毎週金曜日の正午前後にモスクでの集団礼拝が行われるほど、金曜日の礼拝は特別な存在です。
イスラム教徒との会議や打ち合わせでは、礼拝の時間に配慮して予定を組む必要があります。
5-1-3.1年に一度あるラマダン(断食月)
ラマダンはイスラム教徒が日の出から日没まで飲食物、喫煙などを一切摂らない断食を行う期間です。
イスラム暦の断食月に実施され、約1か月続きます。
ラマダン期間中のビジネスシーンでは、日中の集中力が低下し、仕事の生産性が落ちることがしばしばあります。
ラマダンが終わると、断食月の終了を祝う大祭「イード・アル=フィトル(レバラン)」が行われます。
この期間はレバラン休暇となり、多くの人が故郷へ帰省する習慣があります。
日本のお盆や正月にあたる帰省を想像するとよいでしょう。
また、ラマダンやレバラン期間中は犯罪行為が増加する傾向にあるので、ご注意ください。
5-2.商習慣やビジネスルール
日本とインドネシアでは人間関係や時間感覚、モラルの捉え方に大きな違いがあるため、インドネシアの商慣習やビジネスルールを理解していなければ、インドネシア市場への進出は成功しづらいです。
主な商習慣やビジネスルールは、以下のとおりです。
| 商習慣やビジネスルー | 内容 |
|---|---|
| ビジネス時の服装は オフィスカジュアル |
|
| 左手で握手や物を渡す行為はNG |
|
| 対人関係の重視 |
|
| メンツや年上を立てる |
|
| 直接的な不満表明はしない |
|
| 時間に対する柔軟性 |
|
| 渋滞への対応 |
|
| 通信環境の管理 |
|
| コンプライアンス管理 |
|
インドネシアでの商習慣やビジネスルールは、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
「インドネシア進出」の基礎知識 関連記事
- 【2024年版】「インドネシア進出」の基礎知識
- 日系企業がインドネシア進出するデメリット・リスク一覧
- 日本企業がインドネシアに進出して成功した事例 一覧
- 【業界別】日本企業がインドネシア進出に失敗・撤退した事例
- インドネシア進出企業が押さえておきたい一般常識・習慣や宗教事情、ビジネスマナー・タブー 一覧
- 【2025年最新版】インドネシアのビザ(査証)の申請・取得方法を簡単解説
- 【最新版】インドネシアの就労ビザ(査証)の申請・取得方法
インドネシアビジネス 必読記事
\ もっと知りたい/
noteでも記事を更新中!
出張・視察で失敗しない!訪問時に気をつけるポイント3選
2026年02月01日
インドネシアで爆発的に広がる「パデル」と「ピラティス」ブーム【共通の鍵】
2026年01月07日
インドネシア若者達の興味の先は?TOP Youtuber 8選
2025年12月31日
インドネシア消費者、何を買う? なぜ買う?購買心理を読み解く
2025年12月11日
よくあるご質問
インドネシア進出に関する基本情報や、独自ルールに加え、進出の成功・失敗事例などの役立つ情報を配信。
インドネシアでの事業経験者と専門家が進出のサポート・相談も無料で承っています。
メディア運営の代表者はプライム上場企業のインドネシア子会社を8年間現地で経営していた経験があります。
その他エリアはご相談ください。
その他エリアはご相談ください。
会計・法務・労務・人材採用など進出済の企業様からのご相談も多数ございます。
法の解釈や現地当局の回答に疑問をお持ちの場合などもレビューさせていただきます。
お見積もりとあわせてご納得いくまでご検討いただければと思います。